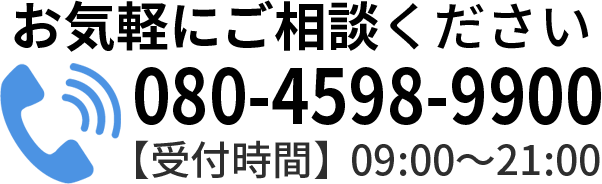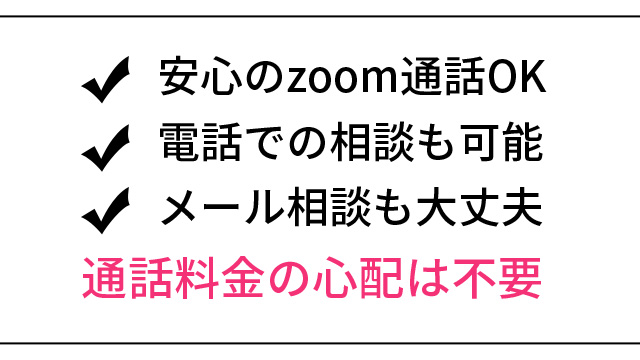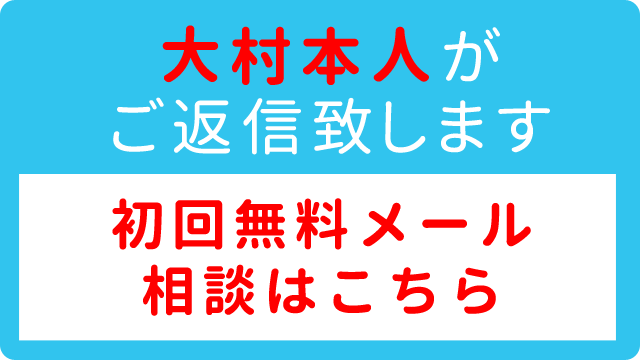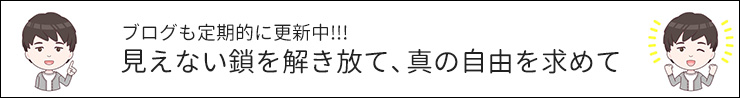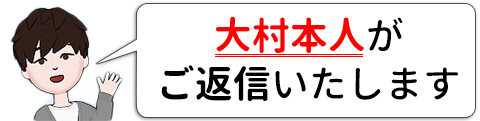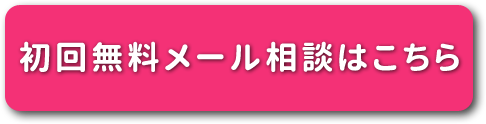まずは自分のことを知ろう
一般的に、共依存の方の思考・行動パターンは、日本では美徳と言われるようなパターンであることが多く、そのために自分のパターンが生きづらいものになっていることに気が付きにくくなっています。
それで苦労してきたわけですから、思い切って一度美徳から離れなければいけません。
美徳というのは、例えば、
- 自分よりもまずは他人を重んじる、
- 相手の気持ちを察せよ、
- 自己否定と言えるほどの遠慮や謙虚さ、
- 異常なまでの恩や義理人情、
- 不必要なほどの正確性や丁寧さ、
等ですね。
これらによって、自分への禁止事項や制限がとても多いのが日本人の特徴です。
共依存を育てる環境が整っている国なのです。
共依存の方の思考・行動パターンはチェックリストに載せた通りですが、何十年にも渡って染みついているそのパターンがなぜできてしまったのか、まずはその分析をします。
「共依存」チェックリストはコチラ ↓
幼少期から現在に至るまで、 一つ一つ丁寧に紐解いていきます。
ご相談内容が夫婦問題であっても、自然と過去の話(生育歴) になっていきます。
夫婦間の苦しいエピソードの中には、必ずと言って良いほど過去にまかれた種があります。
現在の自分が作られたのには必ず過去からの流れがあるのです。
(必ずしも過去の振り返りをするわけではございませんし、振り返ることで辛くなってしまうなら無理に行うことはしません)
自分がなぜその思考・行動パターンをするのか、 そのメリットとデメリットを洗い出します。
洗い出してみると、意外に 自分がメリットだと思っていたことがデメリットだったという発見があります。
- 相手のためにしていたことが、 実は自分のためだった、
- 良く思われるためにやっていたことが、実は被害者体質を育てることにつながっていた、
ということに気が付くこともあります。
そういった気付きを得ることが最初のステップとなります。
「自覚」への勇気を持とう
共依存からの脱却は、自分自身が共依存であると「自覚」することから始まります。
そして自分以外にも同じような生きづらさを抱えた人たちが存在することを知ることも大事です。
今現在なんとなく生きづらさを感じるといった症状が発生している原因は、
- 「家族のせいではない」
- 「私の家族は正常だ」
という不健全な家族で見られる特徴である「否認」です。
それを解除することが必要です。
程度によっては「自覚」に相当な時間と労力が必要になります。
長い間自尊心が傷ついていたわけで、急に自分を信じてがんばっていこうというのは到底無理な話です。
そのため、まずは人に頼れる力を身に着け、人に頼ることから始めましょう。
それが自立への一歩となります。
頼るというと真っ先に「それは依存ではないのか」と考える方が多くいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
そこに自分の意思があるなら、それは依存ではありません。
逆にそこに自分の意思がないなら、依存になります。
つまり、自分の意思がなく、相手のことを妄信してただ従っている状態は依存となります。
また、頼れる人が一人ですとすべてがその一人に集中し、その人との距離感が近過ぎて密接してしまい、依存になりやすくなります。
そのため、頼れる力を身に着けたらできるだけ複数の人(あまり多くてもいけません)に分散させ、適切な距離感を維持しましょう。
そのために私が存在します。
依存させずに自立を促していく存在となります。
下手に、共依存という概念を知らない、頼られることで自分の存在意義を感じるような人に頼ってしまうと、ますます依存心が強くなってしまい、自立から遠ざかってしまいますので、頼る相手を間違ってはいけません。
「依存させてくれる人=優しい人」ではありませんので気を付けましょう。
頼ると好かれる!?
あなたは人に頼ることが苦手ではないでしょうか?
そんなあなたのために人に頼るハードルを下げるお話をしたいと思います。
まず、人は「助けた人が助けた相手に好意を持つ」という習性がある(とある実験で証明されていますがここでは割愛します)、ということを覚えておいてください。
ご相談いただく方の多くは、好かれたい人を助けることで好かれようとします。
先程の習性に当てはめると、自分が助けた側ですので、自分が相手を好きになります(ただし、残念ながら相手からは期待した程好かれることはありません)。
逆に言えば、自分が好かれたい相手から助けられれば、好かれるということになります。
つまり、好かれたい相手に頼ることが好かれるためには必要だということです。
助けた側の心理は、「なぜ助けたのだろう?」→「助けたということは好きなんだ(好きだから助けたんだ)」のようになるのです。
好きでもない何とも思っていない相手をなぜ助けたのか、という矛盾を嫌うという人の性質(認知的不協和)を解消するために、好きだから助けたんだ、と意味を後付けするのです。
- 「人に頼ってはいけない」
- 「自分のことは自分でやらないといけない」
- 「自分を犠牲にして相手に尽くさないといけない」
という風潮が日本では特に根強く、かつ美徳とされていますので、人に助けを求めることに抵抗があると思います。
もちろんこれらも大事なのですが、それだけでは生きづらい上に損をすることになります。
自分ばかりが相手を好きになる一方なわけですからね。
バランスをとるためにも、人に助けを求めるということを意識していきましょう。
自分一人でできるものでも、あえて誰かに頼んでみる、ということをしてみましょう。
頼んだ相手から好意を持ってもらえる、ということもセットでついてきますしね。
共依存・アダルトチルドレンの克服の3段階
共依存やアダルトチルドレンの克服において、成長のプロセスを大きく3段階で示すと、以下のようになります。
- 無自覚
↓ - 自覚があるができない
↓ - 自覚してできる
「①無自覚」と「②自覚があるができない」の間には大きな隔たりがありますが、「②自覚があるができない」と「③自覚してできる」の間にはそれ程差はありません。
カウンセリングは、①から②に移行するのに特に有効です。
②までいってしまえば、③に移行するのにはそれ程時間はかかりません。
②に移行することでほぼ克服していると言って良いです。
それくらい自覚が大事なのです。
自分が共依存であるということを認めることは誰しも不安があると思います。
不安を少しでも和らげるお手伝いをさせてください。
克服の第一歩として何ができるのか

共依存の克服のために何ができるのかについてはたくさんありますが、その中の一部を紹介していきます(順番に意味はないです)。
中には第一歩としてはハードルが高いと感じるものもあると思いますが、難しいものはお客様のレベルに合わせてかみ砕いて簡単なものにしていきます。
具体的に何をしていったら良いのかについては、人によって違いますのでカウンセリング時(「共依存克服プログラム」にて)にお伝えします。
無意識でやってきたことを意識して行動する
長年の習慣として、無意識的に行ってきた行動や思考を一度立ち止まって見つめ直します。
思考停止を防ぎます。
「なぜそれをするのか」と自分に問い、何か(誰か)に動かされるのではなく、自分で自分を動かしている感覚を取り戻します。
反射的に行動しない
例えば、結論を出すことを急かされたり、何かを頼まれたり、迫られたり、そうした状況に直面した際に、感情や習慣に流されてすぐに反応するのではなく、一度立ち止まって自分の意思を確認する時間を持ちます。
この習慣は、思考停止を防ぎ、本当に自分が望む行動を選択する力を養います。
何も考えずにやってきたことを疑い、考え直す
「反抗期」のやり直し、そして和解へのページの「親の価値観を手放す」の所でも記載しましたが、これに近いものです。
「~すべき」「~でなければならない」といった、これまで当たり前だと思ってきた価値観やルールを再検討します。
これは、幼少期に親や周囲から植え付けられた価値観を手放し、自分自身の価値観を再構築するプロセスです。
これにより、他人の言動を真に受けずにワンクッション置くことができ、自分のペースでいられるようになるため、モラハラの被害者になりにくくなります。
また、自分の価値観を押し付けるなどのモラハラ加害者や毒親になることも防ぎます。
先回りしてやらないようにする
- 先回りしてやる
↓ - 言われて(反射的に)やる
↓ - 言われて(意識して)やるかやらないかを決める
のようなステップを意識しましょう。
①と②には自分の意思がありませんが、③には自分の意思があります。
この差は大きいです。
相手が困る前に先回りして手助けをするという行動は、一見親切に見えますが、相手の自立を妨げ、自分自身の存在意義を相手への奉仕に見出している可能性があります。
相手に何かを頼まれたときに、自分の意思で「やるかやらないか」を決める習慣をつけることで、健全な人間関係を築くことができます。
自分の意見を主張する
「何をしたい」「何を食べたい」「どこに行きたい」といった、日常の些細なことからで良いので、自分の意見をはっきりと口にする練習をします。
自分の意見が採用されなくても、「意見を言えた」という事実が重要です。
これにより、自己表現の習慣を身につけ、自己肯定感を高めます。
また、「自分には意思がある」と示すことで、モラハラ気質の人は「この人は支配できないな」と思い、離れてくれます。
自分で選択・決断をする
大きなことから小さなことまで、自分で物事を決める経験を積み重ねます。
人生のレールを誰かに決めてもらうのではなく、自分の意思で選択し、その結果を受け入れることで、根本的な自信が育まれます。
成功しても失敗しても、自分で決めたという経験自体が成長につながります。
親や他人が決めたレールに乗ってきただけの人はどんなに能力が高くても根本的な自信はつきません。
自信がつく順に並べると、
- 自分で決めて成功する
- 自分で決めて失敗する
- 誰かに決めてもらって成功する
- 誰かに決めてもらって失敗する
となります。
自分の弱さを認め、受け入れる
上で紹介した「頼る」「助けを求める」につながります。
「弱い自分」を否定するのではなく、ありのままの自分を受け入れることです。
自分の弱さを認めることで、プライドが邪魔することなく他人に助けを求めることへの抵抗感が減り、孤立せずに生きていく力が身につきます。
完璧であろうとするプレッシャーから解放されることにもつながります。
何かを途中で「やめる」経験を積む
「一度始めたことは最後までやり遂げなければならない」という思い込みを手放す練習です。
時には、自分にとって不利益な人間関係や習慣を途中でやめる勇気を持つことも、健全な自己を保つために必要です。
これにより、執着から解放され、より良い選択肢を見つける柔軟性が生まれます。
「最後まで続けなさい」
「最後まで続けなさい」という風潮に縛られて不要な人間関係を続けてしまう方が多くいます。
親に何気なく言われた方も多いと思います。私もそうでしたが、高校の部活を途中でやめたという経験(成功体験)が、ただ辛いだけの結婚生活を長引かせずに済んだ一因だと思っています。
<関連ページ>
毒親が言いがちな生きづらさを招く言葉
あるものに目を向け、ないものに目を向けない(足るを知る)
持っていないものや欠けているものにばかり意識を向けるのではなく、今すでにあるものに感謝する習慣をつけます。
これにより、常に何かを追い求め続ける虚無感から解放され、満たされた気持ちで日々を過ごせるようになります。
ないものに目を向けている限りは、どんなにあるものが増えても虚無感に苛まれます。
他人との違いを優劣に変換しない
自分と他人との違いを、どちらが優れている、劣っているという評価に結びつけないようにします。
人はそれぞれ異なる個性や価値観を持っているという事実をありのままに受け入れることで、不必要な自己否定や他人への嫉妬から解放されます。
結論を急がない
物事にはっきりとした白黒をつけようとせず、「グレー」な状態に耐える練習をします。
世の中には正解がないこと、曖昧さを受け入れることを学ぶことで、完璧主義を手放し、心の余裕を持つことができます。
1人でいられるようにする
誰かと一緒にいないと不安になるのではなく、一人でいる時間を充実させ、楽しむ方法を見つけます。
これにより、他者への過度な依存から脱却し、自立した精神を養うことができます。
1人で喫茶店などのお店に入れるようにしたり、1人で映画やカラオケなどに行けるようになったり、1人で旅行に行けるようになったり、いろいろとミッションを与えることがあります。
1人でも大丈夫な工夫や考え方をお伝えいたします。
突然友人がいなくなってもゼロから作り出せるようにする
孤独に強くなり、かつゼロから作り出せる力が余裕を生み出します。
一人でも楽しめるし、複数でも楽しめる柔軟さが大事です。
上記の、「一人でいる力を身につけること」と矛盾しているように見えますが、これは他者との関係に執着しないためのものです。
いつでも新たな人間関係や環境を作り出すことができる力を持つことで、特定の誰かにしがみつく必要がなくなります。
ここでは友人を例にしていますが、友人に限らず、ゼロから何かを生み出せる、つまりいつでもどんな時でも自由にコントロールできる自力をつけることで人生に広がりが持てるようになります(他には、自力でお金を生み出せる、等)。
自分の居場所を作る
ありのままの自分を受け入れてもらえる、安心できる場所やコミュニティを見つけることです。
この居場所は、カウンセリングの時間や信頼できる友人関係など、様々な形で存在し得ます。
自己開示の練習をしましょう(希望があればカウンセリングで行いますよ)。
あまりにも警戒して自分を閉ざしていては居場所は作れませんからね。
褒め言葉を受け取る
褒められたときに「そんなことないです」と否定するのではなく、素直に「ありがとう」と受け入れるようにします。
褒め言葉を否定することは、自分自身を否定することにつながり、自己肯定感を下げてしまうからです。
また、あまりにも否定するなら、褒めてくれた人にも失礼になることがあります。
自分を卑下する言葉を発さない
「自分はダメだ」「どうせ私にはできない」といった、自分を卑下する言葉を口にするのをやめます。
言葉は自分の思考や感情に大きな影響を与えます。
自分が発した言葉は自分で聞くことになるからです(脳に影響を与えます)。
このようなネガティブな言葉を避けるだけで、自己否定のサイクルを断ち切る一助になります。
言葉が自分を作りますのでやめましょう。
無理矢理感のあるポジティブ言葉はよくありませんので、それを勧めるつもりはありませんが、最低でもネガティブな言葉はできるだけやめましょう。
やめるだけでプラスになります。
D言葉を言わない
「でも」「だって」「どうせ」「できない」という言葉をできるだけ使わないようにしましょう。
自己暗示としても対人コミュニケーションとしても、以下のような悪影響を及ぼします。
- 行動や挑戦を止めてしまう
→「やらない理由探し」に意識が向き、チャンスを逃す。 - 建設的な話ができなくなる
→前向きなアイデアや協力が生まれにくくなる。 - 信頼や協力の空気を壊す
→否定的な返答が続くと「話しても無駄」と感じさせる。 - 場の雰囲気を重くする、しらけさせる
→会話や場のエネルギーを下げ、前向きな発想が出にくくなる。
自分の立ち位置を理解する
<関連ページ>
他人と比べない
他人と自分を比較することで、幸福度を測ったり、自分の価値を決めたりするのをやめます。
SNSなどを断つことも一つの方法です。
自分自身の成長や変化に焦点を当てることで、不必要な承認欲求から解放され、心の平穏を得ることができます。
よく言われることですが、同じ「比べる」なら過去の自分と比べましょう。
不特定多数からの承認欲求を断つ
SNSを断つことも一つです。
SNSなどで、多くの人からの「いいね」や称賛を求めることをやめます。
不特定多数からの承認は、一時的な満足感しかもたらさず、自分を蝕む原因になります。
さらにはSNS依存の原因にもなります。
満たされるために必要な「いいね」などの数がどんどん大きくなり、際限がなくなることがこわいですからね。
本当に大切な人との関係性や、自分自身の内面から来る満足感を大切にすることが重要です。
SNSの違和感
周囲を見渡すと幸せな人々で溢れている、そんな風にあなたの目には映るかもしれませんが、果たして本当に周囲の人々は幸せなのでしょうか。
私ももちろんSNSを利用していますが、どうも違和感を持ってしまうのです。
「この違和感は何だろう?」と思って考えていると閃きました。
それは、あまりにも幸せ全開な投稿が多い気がしないか、自慢全開な投稿が多い気がしないか、と(特にFacebookとInstagram)。
私の仕事柄そう感じるだけかも、と最初は思いましたがそうでもないようです。
「結婚しました」という報告はあっても「離婚しました」という報告は見かけませんよね?
実際は報告しづらいだけで、今これを読んでいるこの瞬間にも離婚届は出されています。
多少自分を卑下する内容であっても、よくよく読んでみると遠回しな自慢である場合が多いです。
不幸ばかりの投稿では読まれなくなるだろうし、友人に少し距離を置かれるかもしれないという恐怖心を差し引いても、あまりにも幸せな投稿が多い気がしませんか?
何が言いたいかというと、SNSの投稿の内容と現実にあまりにも差があるということです。
もちろん、本当は自分は不幸なことが多くて生きづらさを抱えているという自覚があるけれど、そんな不幸を見せるなんて恥ずかしい、友人が離れていってしまう、だから不幸な内容は投稿しない方が良いだろう。
そう思って結果的に数少ない幸せな事柄を厳選して投稿している人もいるかと思います。
こういった人は自覚している分だけ安心かもしれません。
このように幸せそうに見える人々も意外に生きづらさを抱えています。
そんな人たちから一歩抜け出しませんか?
一緒になって偽りの幸せで武装をする必要はないのです。
不特定多数の人からの承認欲求は自分を蝕みます。
もう一度改めて言いますが、共依存から脱却するプロセスにおいて一番最初にしなければならないことは、自分自身が共依存であるという「自覚」です。
そして自分以外にも同じような生きづらさを抱えた人たちが存在することを知ること。
この第一歩が大きな前進を生みます。
最終目的地である、
「本来の自分でいられる安全な場所」
を見つけ出すことへの第一歩になります。
人間関係の再構築
共依存問題を抱えた人は、夫婦間だけでなく他の人間関係においても不健全である場合が多いです。
自尊心が低い人など自分と同じような人との付き合いが多く、そしてそのような人と付き合う方が楽だと思っています。
自分を必要としてくれるような人を無意識のうちに選んでしまう。
心当たりがある人もいるのではないでしょうか。
逆も然りです。
自ら選んでしまうこともあるけども、そのような自分と同じような人がいつも自分に寄ってくる。
そんな経験も多いのではないでしょうか。
これもまた無意識のうちに自分に寄ってくるように仕向けている場合が多いです。
この無意識こそが曲者です。
意識してこの自分の特徴に目を向けていく必要があります。
私のところには夫婦どちらか一方、あるいは夫婦共に共依存問題を抱えている方がいらっしゃいますが、それは私が想像していたよりもとても多いです。
自覚されていない方も含めれば潜在的にもっとたくさんいらっしゃるのだと思います。
私のところにいらっしゃる共依存に悩まされている方の多くは、自分に自信がなく、自分以外の人たちは自分を傷つける存在だと思っているために、親密な関係を恐れている方が多いです。
深い関係でいるよりも一人の方が安心すると考えています。
そのままの自然体でいようとすることは危険以外のなにものでもない、というように。
自分は共依存であると自覚し、受け入れて、変わっていけば、周りの人間関係も変わっていきます。
変われますので安心してください。
これまで大変苦労してきたと思いますが、これから治していけば良いのです。
夫婦間の共依存を克服できれば、自ずと他の人間関係も健全なものに変わりますよ。