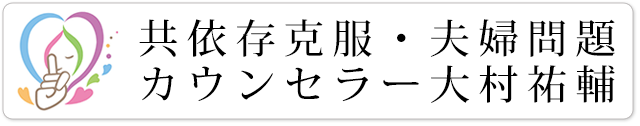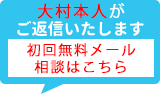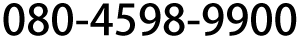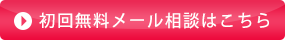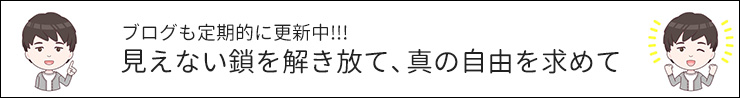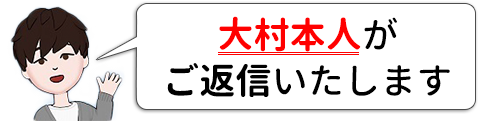愛着障害が引き起こす共依存の仕組み:なぜいつもつらい恋愛を繰り返すのか
愛着障害とは

愛着障害とは、その名の通り、
“幼少期の愛着形成に何らかの問題を抱えている状態”
をいいます。
愛着(=アタッチメント)とは、
「特定の人(母親等の養育者)との間の情緒的なきずな」
を表す言葉です。
幼少期(特に生後3ヵ月~1歳半)、すなわち「愛着の形成期」に、この愛着が何らかのかたちでうまく形成されず、そのまま何の対処もせずに大人になってしまうと、情緒面や人間関係の面で支障をきたすことになります。
具体的には、幼少期に、
・両親からの虐待やネグレクト(無関心、無視)、
・両親の離婚や死別、
・両親からの支配(モラハラ、価値観の押し付け)、
・きょうだい間の差別や比較、
・両親からの条件付きの愛情等による歪んだ愛情、
等があると、愛着形成に問題を抱えやすくなります。
当然自己肯定感が育まれるはずはなく、いわゆる「生きづらさ」を抱えて生きることになってしまうのです。
自ずとアダルトチルドレンの特徴を持つこととなり、恋愛依存や共依存、モラハラ(加害者にも被害者にもなりうる)等にも関係していきます。
これらの根幹をなすのが、愛着障害なのです。
大人の愛着障害~愛着スタイルの分類・特徴~
次に、愛着障害による、愛着スタイルの分類や特徴を見ていきます。
愛着スタイルには、「安定型」「不安型」「回避型」「恐れ・回避型」があります。
幼少期の親との関係によって、どの愛着スタイルになるかが大きく変わっていきます。
この愛着スタイルがどの型かによって、人間関係においてどんな関係性を求めるか、どんな関係性を快適と思うか、が変わってきます。
この愛着スタイルの特徴は、特に恋愛面で色濃く表れます。
自分の愛着スタイルを知っておくことはとても大切です。
<安定型の特徴>
・対人関係において大きな問題が起きることがほとんどなく、何か問題が起きそうになっても、自分の気持ちを主張でき、かつ相手の気持ちを受け入れることができます。
→基本的に人を肯定的に捉えることができ、信じることができるからです。
・困った時には、人に助けを求めることができますし、困った人を見かけた時には人を助けることもできます。
→それは言うまでもなく、親から十分に愛された、受け入れてもらえた、という基本的安心感によるものであり、それが他者に対しての安心感につながり、人に愛を与え、愛を受け取ることができるのです。
・捉え方に歪みがなく、他者を肯定的に捉えるため、当然他者からも肯定的に捉えてもらえるようになり、人間関係においていつも良い循環を作ることができます。
<不安定型-不安型の特徴>
・常に不安感を持ち、自信を持って人と接することができません。
→そのため、常に消極的かつ受動的で、相手に合わせるということが基本姿勢となります。
・相手の顔色を極端にうかがい、常に嫌われないようにすることを優先します。
・自己肯定感が低く、自分は嫌われる存在だと思っているため、相手の一挙一動をすべて否定的に捉える傾向にあります。
・恋愛においても、「相手がいないと生きていけない」というくらい依存的となり、少しでも相手からの愛情が薄れると不安になり、相手に迷惑をかけるほど連絡をしたり、試し行動をしたりします。
<不安定型-回避型の特徴>
・基本的に人を信頼していないため、人と親密になることを避けようとします。
→そのため、すべての人間関係が浅い関係性となります。
・「人と親密になってもどうせ人は自分から離れていくのだろう」と思っているため、離れられてしまって傷つくことを避ける行動をとります。
→したがって、最初から親密にならないようにする、という選択をします。
・親密になることを避けるため、なるべく人に関心を示さず、自己開示もしないようにします。
→そのため、周りの人からするととても分厚い壁を感じ、近付かないようにします。
<不安定型-恐れ・回避型>
・不安定型の不安型と回避型の両方の特徴を持ちます。
《参考文献・引用》
『愛着障害-子ども時代を引きずる人々-』
岡田尊司 著 2011 光文社新書
不安型と回避型の共依存

不安型女性×回避型男性
一番多い愛着障害のご相談は、不安型と回避型の夫婦(またはカップル)で、不安型側の方からのご相談です。
だいたいにおいて、不安型=女性、回避型=男性、のケースが多いです。
不安型と回避型が真逆なのに惹かれ合って一緒に居続けてしまう理由は、お互いの傷を補完し合う関係だからです。
共依存へと発展する要因です。
不安型と回避型は、それぞれ幼少期の親との関係の中で「愛されるための戦略」を身につけてきました。
不安型は「愛されるには必死にしがみつく必要がある」と学び、回避型は「親密さは危険だから距離を取るべきだ」と学びます。
そのため、大人になっても無意識のうちに「知っている形の愛」「慣れている形の愛」を再現しようとし、相性が悪いのにお互いに引き寄せられてしまいます。
不安型は、「見捨てられたくない」「愛を確認したい」という欲求があり、相手にしがみつこうとします。
回避型は、「束縛されたくない」「距離を保ちたい」という欲求があり、親密さを避けようとします。
不安型は、回避型の「冷たさや距離感」に対して「愛を証明してもらう挑戦」として捉え、必死に追いかけます。
回避型は、それを「面倒だ」と思いながらも、「ここまで自分を求めてくれる人は他にいない」と感じてしまい、完全には離れられません。
この関係では、「不安型が追い、回避型が逃げる」というパターンが繰り返され、定着していきます。
不安型は、相手が離れそうになるたびに「もっと頑張れば愛される」と思い、努力を続けます。
一方で、回避型は「適度に距離を取れば相手が追ってくる」と学習し、余計に逃げるようになります。
不安型は「回避型がたまに見せる優しさ」に依存しがちです。
例えば、普段そっけない回避型が、たまに優しくすると、「やっぱりこの人は私を愛してるんだ」と思い込んでしまい、離れられなくなります。
これは「間欠強化」と呼ばれ、ギャンブル中毒と同じ心理メカニズムです。
→間欠強化についてはこちら
また、回避型も「相手が自分を必要としてくれる安心感」があるため、完全に関係を断ち切ることができません。
どちらも苦しいのに離れられない状態に陥りやすく、こうして共依存関係になってしまうのです。
やがてお互いの傷を深め、安心感のある関係を築くのが難しくなります。
解決には、まず自分自身の愛着パターンを理解し、相手に依存するのではなく、自分の内側で安定を育てることが重要です。
回避型男性×マッチングアプリ
マッチングアプリを利用する際は注意した方が良いです。
というのは、回避型の男性にとって、マッチングアプリというのはとても都合の良いものだからです。
回避型の男性のニーズとマッチングアプリはとても相性が良いのです。
気軽に女性と出会うことができ、気軽に別れることができるからです。
自分の意に少しでも沿わない人だと判断すればすぐに別れて、他の女性に飛びつくことができるなんて、回避型の男性にとってこんな都合の良いアプリはありません。
つまりそれだけ回避型の男性と遭遇する率が高いということになります。
回避型の男性がマッチングアプリにとどまるからです。
ここ数年回避型の男性はどんどんマッチングアプリに参入していますし、今後も参入が増えていくと思われます。
また、マッチングアプリが回避型の男性を増やしている側面もあります。
元々は特定の一人の人と真剣な付き合いを求めていた男性も、簡単に付き合って簡単に別れられる気軽さから、変に成功体験を積んでしまい、回避型の恋愛を好んでいくようになるのです。
これらが何を意味するかというと、ただでさえ回避型の男性との遭遇率が高いのに、今後さらに回避型の男性との遭遇率がどんどん上がっていく、ということです。
そのため、まじめな出会いを求めている女性は、絶対に回避型の男性の生態について知っておかないと痛い目にあいます。
人生において何よりも大事で貴重な時間を奪われ、
トラウマレベルの傷を負わされ、
男性不信に陥ってその後の恋愛も上手くいかない、
ということが起こってしまうからです。
回避型の男性と良い関係を築いていくためにも、回避型の男性から離れるためにも、いずれにおいても女性側の共依存体質や恋愛依存体質からの脱却は必須だと思います。
特に愛着障害の不安型の女性からのご相談が多いですが、回避型の男性とはものすごく相性が悪いですので、当然そのままでは良い結果にはなりません。
一緒にご自身の改善(安定型への改善)と回避型男性についての研究と対策をしていきましょう。
恋愛依存のメカニズム
愛着障害が恋愛依存を引き起こす理由
次に、恋愛依存との関係性です。
愛着障害を抱える人が恋愛依存になりやすいのは、幼少期に満たされなかった愛情への渇望が根深く残っているからです。
本来であれば親から無条件の愛を受けることで安定した自己肯定感を育むはずが、それが叶わなかった場合、大人になってもその欠けた部分を埋めようとする衝動が続きます。
特に不安型の愛着スタイルを持つ人は、「愛されるためには必死に努力しなければならない」という信念を持っています。
そのため、恋愛においても、相手から愛されるために自分を犠牲にしてでも尽くそうとし、相手の存在なしには自分の価値を感じられなくなってしまうのです。
この状態では、恋人は単なるパートナーではなく、自分の存在意義を証明してくれる重要な存在となります。
だからこそ、相手を失うことへの恐怖が異常に強くなり、束縛や監視といった行動に走ってしまうのです。
恋愛依存の典型的な症状と行動パターン
恋愛依存に陥ると、日常生活のすべてが恋人中心になってしまいます。
朝起きてから夜寝るまで、常に相手のことを考え、相手からの連絡を待ち続ける状態になります。
仕事や友人関係、趣味などがすべて二の次になり、恋人との関係だけが人生の最優先事項となってしまいます。
相手の行動や言動を過度に気にするようになり、少しでも冷たい態度を取られると「嫌われたのではないか」「他に好きな人ができたのではないか」と不安に駆られます。
その結果、相手のSNSを頻繁にチェックしたり、行動を監視したりする行動に出てしまいます。
また、相手から愛されていることを常に確認したくなり、「私のこと好き?」「一番大切な人?」といった質問を繰り返したり、わざと試すような行動を取ったりします。
これらの行動は、一時的に安心感を得られても、根本的な不安は解消されないため、さらにエスカレートしていく傾向があります。
恋愛依存から共依存への発展過程
最初は一方的な恋愛依存だったものが、時間が経つにつれて共依存関係へと発展していくケースが多く見られます。
これは、依存される側も次第にその関係に慣れ、相手から必要とされることに安心感や優越感を感じるようになるからです。
依存する側は「この人がいないと生きていけない」と感じ、依存される側は「この人は私がいないとダメな人」と感じるようになります。
こうして、お互いが相手の問題を解決し合う関係性が出来上がり、健全な距離感を保つことが困難になっていきます。
共依存関係では、お互いが相手の感情や行動に責任を感じるようになり、自分の人生よりも相手の人生を優先するようになります。
これは一見献身的に見えますが、実際には両者の成長を阻害し、真の意味での愛情関係とは言えない状態なのです。
恋愛依存から抜け出すための具体的対処法
恋愛依存や共依存から抜け出すためには、まず自分軸を確立することが最も重要です。
自分軸とは、他人の評価や反応に左右されない、自分自身の価値観や信念に基づいた生き方のことです。
恋愛依存に陥っている人の多くは、自分の価値を相手からの愛情や評価で測ってしまっています。
しかし、本来の自分の価値は他人が決めるものではありません。
自分が何を大切にし、どんな人生を送りたいのかを明確にし、それに向かって行動していくことが大切です。
一人の時間を楽しめるようになることも重要なポイントです。
恋愛依存の人は、一人でいることを極端に恐れ、常に誰かと一緒にいたがる傾向があります。
しかし、一人の時間こそが自分自身と向き合い、内面を充実させる貴重な機会なのです。
読書や映画鑑賞、散歩や料理など、一人でも楽しめる活動を見つけることから始めてみてください。
最初は不安に感じるかもしれませんが、次第に一人の時間の価値を実感できるようになります。
また、相手に求めすぎない健全な関係性を築くことも大切です。
恋愛においては、お互いが独立した個人として尊重し合い、適度な距離感を保つことが重要です。
相手に依存するのではなく、お互いが成長し合える関係を目指しましょう。
これらの変化は一朝一夕には起こりません。
時間をかけて少しずつ自分を変えていく過程が必要です。
焦らず、自分のペースで取り組んでいくことが成功への近道です。
<関連ページ> 克服方法(考え方&ワーク)の一部を載せています。あなたに合った内容を、順番を考えながら提示し、実践いただいています。
・克服の第一歩として何ができるのか
・『共依存克服プログラム』の主な内容
インナーチャイルドを癒す
機能不全家族で育った人はインナーチャイルドが傷ついています。
インナーチャイルドとは、
「内なる子ども」
と一般的に言われています。
誰しもが身体は大人になっても、心の中には幼少期の心が残っています。
インナーチャイルドが傷ついていると、実年齢にそぐわない幼い子どもの頃の心が現れやすくなります。
子どもの頃に満たされなかった心は大人になっても引き継いでいくものだからなんですね。
どんなにお金や物、地位や名声を得ても、満たされない人がいるのはインナーチャイルドの傷つきが原因です。
自分でも気がついていないことがあります。
「あんなに自立した財力もあり地位もあり器の大きい優しいご主人(奥さん)がいるのにどうしてあの人はいつも満たされないのだろう…」
と周囲の人が思っても本人だけがそのありがたさに気がついていないことも多くあります。
どんなに外側から傷ついた心を埋め合わせても、すぐにカラになってしまうんですね。
幼少期の心と改めてしっかり向き合うことが癒しの一歩です。
抽象的な表現になってしまいますが、
外側から満たすのではなく、内側(自分)から満たすことができるようにしましょう。
インナーチャイルドを癒すことが共依存関係になることを防ぐことにもつながるのですよ。
共同作業で癒していきましょうね。
| この記事を書いた人 | |
| 共依存・夫婦問題カウンセラー大村祐輔 9年間で約800人、60分×約13,000回のカウンセリング実績から得た知識や経験を還元できるよう日々尽力しています。 大村の理念は「夫婦問題を解決して終わりじゃない」「離婚して終わりじゃない」「根本からの自己改革」です。 共依存で悩むあなたに「とことん付き合う」の精神で活動しています。 日本学術会議協力学術研究団体 メンタルケア学術学会認定 メンタルケア心理士 資格番号E1607030023 一般社団法人 ハッピーライフカウンセリング協会認定 離婚カウンセラー 会員番号200017 →詳しいプロフィールはこちら |
|