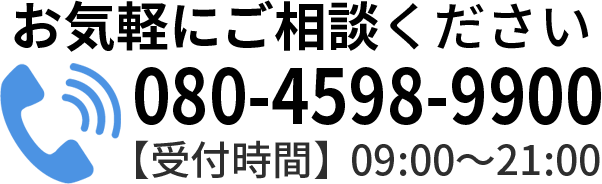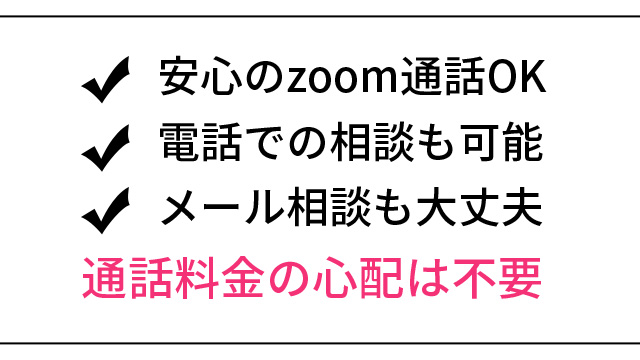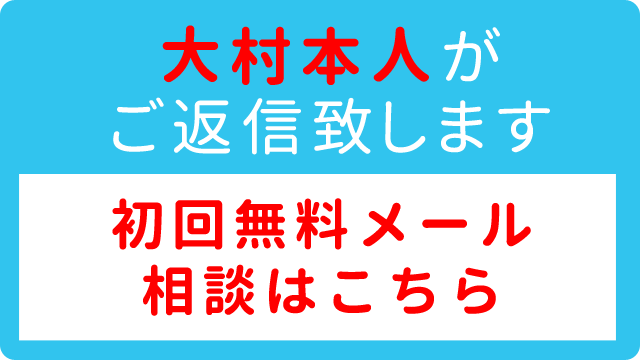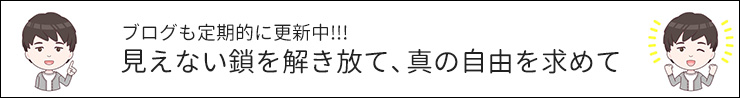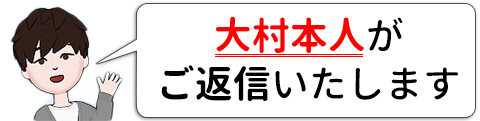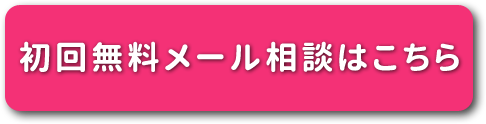【この記事でわかること】
- 「謝るけど直らない人」の心理構造
- NPD(自己愛性パーソナリティ障害)の“支配を維持する謝罪”とは?
- ASD(自閉スペクトラム症)の“納得しないと謝れない構造”と“応急処置的謝罪”の仕組み
- 定型発達の人ができる“誠意ある謝罪”との違い
- それぞれにどう関われば、期待や疲弊を減らせるか
一応「ごめん」と謝罪の言葉はあるものの、何度も同じことを繰り返す人、あなたの身近にそんな人はいませんか?
こういう人が夫や妻のような身近な存在ですと、謝罪の言葉があるだけに、なかなか期待が減っていかずに振り回され、カサンドラ症候群のような状態に陥ることがあります。
「むしろ謝罪の言葉がない方が、はっきりと”離れるべき人”とわかるので良いくらいだ」とおっしゃるクライアントさんも多いです。
このような行動(謝罪はあるが変わらない)は、自己愛性パーソナリティ障害(以下NPD)の人にも、自閉スペクトラム症(以下ASD)の人にも見られることがあります。
しかし、その「ごめん」の意味と構造はまったく異なります。
この記事では、カウンセラーとして多くの事例を見てきた経験から、NPDとASD、そして定型発達の人の“謝罪”の本質的な違いを書いていきます。
謝罪の意味について

NPDの人
NPDの人の「ごめん」は、自分の立場を守るための戦略的な言葉です。
目的は「相手を安心させる」ことではなく、「支配関係を崩さず、自分に主導権を戻すこと」です。
下手に出ているように見えても、実際には“支配の維持のための演出”であり、内省や行動の修正は伴いません。
そのため、時間が経てばまた同じことを繰り返します。
彼らにとって「謝ること」は“反省”ではなく“武器”なのです。
ASDの人
一方、ASDの人が「ごめん」と言う場合、それはしばしば納得したときに限られるのが特徴です。
ASDの人にとって謝罪とは、「自分が悪かったと理解できた時にするもの」。
つまり、相手が傷ついたという“結果”だけでは謝れないことが多いのです。
「相手が怒っている」「相手が悲しんでいる」という感情よりも、「自分が何をしたのか」「なぜそれが悪かったのか」という論理的な整合性が優先されます。
このため、「相手が傷ついた」という事実に対して謝罪がないケースがよくあります。
「自覚がない」とか「悪気がない」のであれば、謝罪する必要はないと思いがちなところがあるのです。
これは決して冷たさや悪意ではなく、「自分の中で理解できないことには言葉が出ない」──というASD特有の情報処理の仕組みです。
しかし、周囲が「まずは相手が傷ついたんだから謝れよ」と言うことで、“とりあえずの応急処置的な謝罪”を覚えるようになります。
そして、「とにかく謝らないと空気が悪くなる」「理由はわからないけど、ごめんと言っておけば丸く収まる」という、形式的な謝罪スキルが身につきます。
ですが、どんな流れであれ、理解できていない限り行動の変化は起こりません。
「ごめん」は言えても、その背後にある意味づけが伴わないため、根本的な学習には結びつかないのです。
謝罪後について
NPDの人
NPDの人には基本罪悪感は生まれません。
生まれたとしても一瞬で、それを保持できません。
罪悪感は彼らにとって「自分の価値を脅かす不快な感情」だからです。
その不快さを回避するために、「そんなつもりじゃなかった」「お前が誤解した」などの自己正当化が起きます。
こうして罪悪感は「自分は悪くない」という形に変換されてしまうのです。
ASDの人
一方、ASDの人は「悪かった」と感じる瞬間はあります。
ただしそれは、“自分が悪いと納得した時点”でしか起こりません。
多くの場合、「相手が傷ついたから謝る」ではなく、「自分が間違っていたから謝る」という構造で成り立っているため、相手の感情面をおざなりにしてしまう傾向があります。
さらに、「どの部分が悪かったのか」を構造的に理解できないため、「怒られた=悪かった」の域で終わってしまい、再発防止には繋がりにくいのです。
このように、
①理解が伴わず謝罪が出てこない
②周囲に促されて出る表面的な謝罪
が特徴です。
自覚について
NPDの人
NPDの人は、「同じことを繰り返している」自覚があることが多いです。
それでも変えないのは、その行動が有効に機能しているからです。
「謝れば相手は許す」「結局、離れない」──この経験が“支配の成立”として強化されていきます。
つまり、謝罪そのものが支配の一部になっているのです。
ASDの人
一方ASDの人は、「同じことを繰り返している」という自覚が薄いです。
状況判断やパターン認識が苦手なため、少し条件が変わるだけで「別の出来事」として処理してしまいます。
そのため、周りの人は「何度言っても伝わらない」と感じることが多いのです。
謝るタイミングについて
NPDの人
NPDの人は、追い詰められた時にだけ謝る傾向があります。
相手が離れそうになった時、立場が危うくなった時──その「危機回避」が目的です。
ASDの人
ASDの人は、その場で即座に謝る(回避型)か、フリーズして謝らないが、後から時間をおいて謝る(遅延型)かの両極端です。
どちらの場合も、「理解」よりも「状況回避」や「納得の有無」で動いているため、行動変化には繋がりにくいのが特徴です。
対応策について
NPDの人
NPDの人には、基本的に距離を取ることが第一です。
「理解してもらおう」とするほど巻き込まれます。
どうしても関係を続けたい場合は、言葉ではなく行動で判断する姿勢を徹底してください。
ASDの人
ASDの人には、感情的な言葉ではなく具体的な説明が必要です。
「冷たかった」ではなく「話しかけたのに返事がなかった」など、行動ベースで伝えることで再現学習がしやすくなります。
ただし、理解はあくまで“具体レベル”にとどまりやすいため、状況が変わると「前回と同じ」と気づけないこともあります。
彼らの「わかった」は「具体的に理解した」という意味であり、本質的に理解したという意味ではない場合が多いです。
悪気がないからといって許す必要はありません。
共依存体質の人は許してしまいがちですが、「悪気がないのに許せない自分が悪い」と罪悪感を抱く必要もありません。
言うべきことは言っていかないといけません。
定型発達の人の謝罪
最後に、比較対象として、定型の人の謝罪について見ておきましょう。
定型発達の人の謝罪は、“関係を修復すること”そのものが目的です。
謝ることで「関係を再構築する」ために、感情・言葉・行動が一貫しています。
1. 感情理解の深さ
定型の人は「相手の心の状態」を想像しながら言葉を選びます。
「嫌な思いをさせてしまってごめんね」「あの時の言い方が冷たく聞こえたかもしれない、ごめんね」などのように、ここには、「自分がどう思っているか」よりも「相手がどう感じたか」が主軸になっています。
2. 再発防止意識の自然な内在化
定型の人は、「信頼は行動で回復する」という感覚を持っているため、謝罪のあとは自然と行動修正を行います。
それは「努力」ではなく「当然のこと」として身体化されています。
3. タイミングの絶妙さ
相手が怒りのピークにいるときではなく、“受け取れるタイミング”を感覚的に読み取って謝ります。
だから、謝罪が感情的にも実際的にも機能しやすいのです。
4. 社会的メタ認知
定型の人は「この言葉をどう受け取られるか」を自然に想像します(「します」であって「できます」ではない)。
結果として、攻撃的でも卑屈でもない、ちょうどよい謝罪につながるのです。
この“社会的センス”が、NPD・ASDとの最大の違いです。
まとめ
「ごめん」と言う人の、その後の行動が変わるとは限りません。
NPDの人は、わかっていても直さない。
ASDの人は、わかっていないから直らない。
定型発達の人は、相手の心を理解し、行動で信頼を回復させようとします。
NPDは変わる意志がなく、ASDは理解が追いついていない。
大まかにですが、このように把握しておくと良いと思います。
いずれにしても、大切なことは、「言葉」ではなく「行動」を見ることです。
もしその謝罪が、あなたへの支配や応急処置的な意味合いでしかないのなら、その人との関係を考えた方が良いと思います。