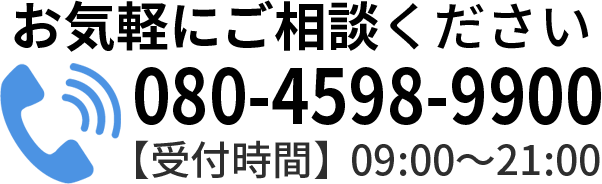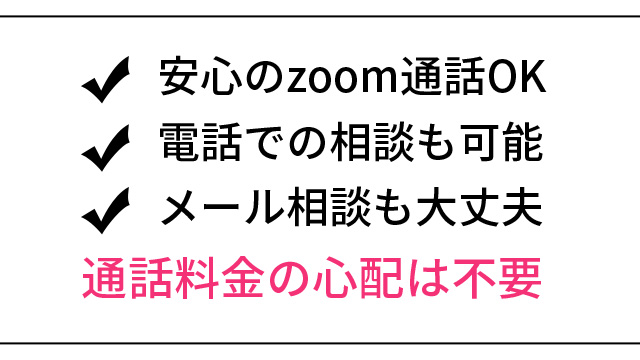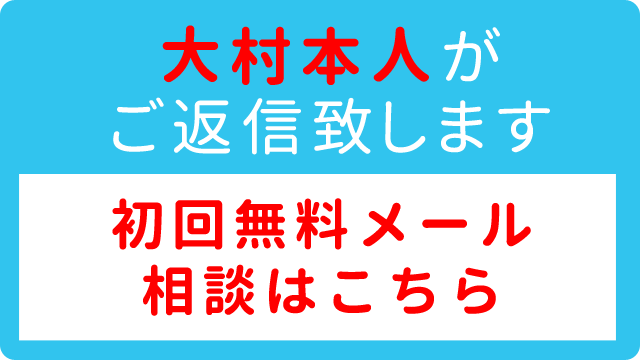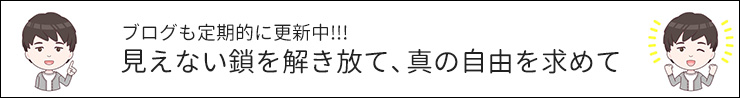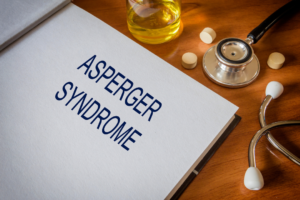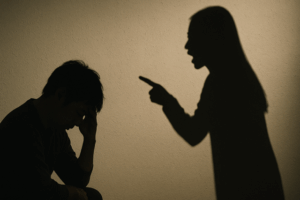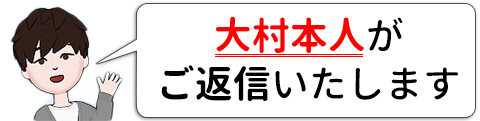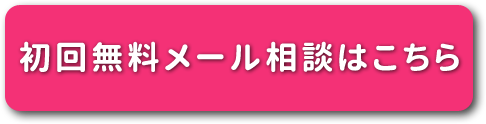「わかってくれない」には2種類ある
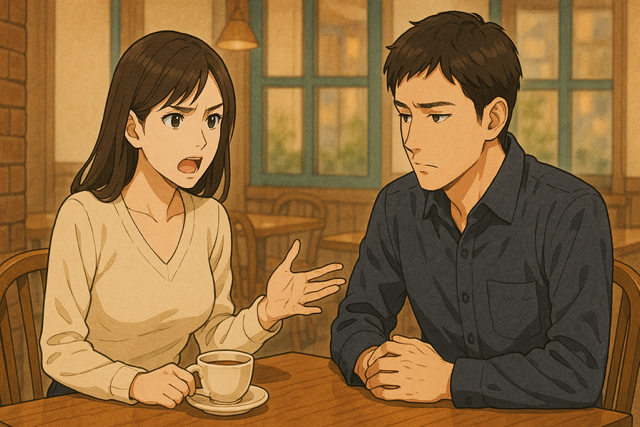
「わかってくれない」には、大きく分けて2種類あります。
ひとつは、カサンドラ症候群に陥っている人が口にする「わかってくれない」です。
これは、パートナー(夫や妻)や身近な人に何度も、根気強く、丁寧に説明をしても伝わらない、その絶望感から出る言葉です。
ここには伝える努力の蓄積があり、説明も工夫されています。
それでも相手に届かないからこそ、「わかってくれない」と嘆かざるを得ないのです。
もうひとつは、十分な説明をしていないのに「わかってくれない」と嘆くケースです。
こちらは、説明の不足や伝え方の偏りに本人が気づかず、「察してほしい」という強い思いで相手を責めてしまうタイプです。
今回の記事で扱うのは、後者の「伝えていないのに、わかってくれないと嘆く人」についてです。
誤解してほしくないのは、この記事はカサンドラ症候群の方に向けたものではない、ということです。
カサンドラの方はむしろ「伝える努力をやめない人」であり、今回のテーマとは正反対の立場にあります。
「わかってくれない」と嘆く人とはどういう人か
「わかってくれない」と嘆く人に共通するのは、自分の説明が足りなかったのかもしれないという視点が欠けていることです。
女性に多い傾向があります。
確かに男性の方が細かい部分で理解が及ばないところはあると思います。
同じ男性として残念ではあります。
しかし、すべての男性がそうだということはなく、女性と同じくらい理解できる人もいるし、それ以上の人もいます。
そんな理解できる側の男性に対しても、「わかってくれない」と嘆く人がいるのです。
ここで重要なのは、相手が他の人とは普通にコミュニケーションを築けているにもかかわらず、自分との間だけうまくいかない場合、その原因は相手ではなく自分の側にある可能性が高いということです。
つまり「わかってくれない」と嘆く人とは、自分の説明不足や経験の乏しさからくるズレに気づかず、相手に責任を押しつけてしまう人だと言えます。
機能不全家族で育った影響
「わかってくれない」と嘆く人の多くは、機能不全家族育ちであることが多いです。
子どもの頃から、親や身近な大人にこう言われ続けた経験はありませんか?
「あなたの考えは間違っている」
「そんなこと言っても仕方ない」
「黙って親の言うことを聞きなさい」
このように、自分の話を真剣に聞いてもらえず、意見を押し付けられてばかりの環境では、「自分の言葉は意味がない」「どうせ理解されない」という無力感が心に刻まれます。
その結果、親以外の人間に対しても「理解されないだろう」「拒絶されるだろう」という恐怖を抱き、深い関わりを避けるようになります。
本来なら、友達や先生、職場の人とのやり取りを通じて「人はどのくらい説明すれば理解してくれるのか」「どこまで許容してくれるのか」といった境界を学んでいくはずです。
しかし、その経験を積めないまま大人になると、会話の勘どころが身につかず、すぐに「わかってくれない」と感じやすくなってしまいます。
大人になって表面化するコミュニケーションの歪み
大人になっても、子ども時代の体験は根深く残ります。
コミュニケーションにおいて、以下のような行動が典型的なものとなります。
説明が不足して相手が混乱しても「察してくれない方が悪い」と思う
抽象的な言葉ばかりで、相手が理解できない
遠慮しすぎて本当に大事なことを伝えられない
相手の限界を超える要求を「当然だ」と押し付けてしまう
――こうしたことをしていませんか?
会話の勘どころ
ここで重要なのは、いろいろな人とのコミュニケーション経験が質においても量においても乏しい人は、「自分の説明が足りなかったのか」それとも「相手の理解力が不足しているのか」、そのようなことの見分けがつかないという点です。
私はこれを会話の勘どころと呼びますが、この勘どころを身につけるには、多種多様な人とやり取りしてきた経験が不可欠です。
その経験が乏しいと、いつも「わかってくれない」と相手の責任にしてしまいやすくなります。
カウンセラーに理想を投影してしまう心理
この傾向は、カウンセラーとの関係で強く現れることがあります。
毒親育ちやモラハラ被害を長く経験した人にとって、カウンセラーは「初めて安心して話せる相手」です。
だからこそ、「何も言わなくても全部わかってくれる」「自分の気持ちを神様のように理解してくれる」と理想化してしまいます。
<関連ページ>境界性パーソナリティ障害の特徴の「理想化」に近い状態になってしまいます↓
ところが、カウンセラーも人間です。
超能力者でもエスパーでもありません。
言葉にしなければわからないことはいくらでもあります。
クライアント:「先生なら、私の気持ちが全部わかりますよね?」
カウンセラー:「私はあなたの言葉を通して理解していきたいです。だからこそ、どう感じたのか教えてもらえますか?」
こうしたやり取りで、「ああ、伝えなければ伝わらないのか」と理解できる人は回復に向かいます。
しかし「わかってくれない」と不満を募らせてしまう人は、せっかくの関係を壊してしまいかねません。
カウンセリングにおける“わからなさ”の質の違い
例えば、カウンセリングでクライアントさんがこのように尋ねてくることがあります。
クライアント:「あのことについてどう思いますか?」
カウンセラー(心の声):「“あのこと”とは、先週の家族の話?それとも仕事の悩み?それとも今日の冒頭に触れた体調のこと?」
丁寧に聞き、理解して記憶している人ほど、“あのこと”について候補が複数浮かび上がり、どこからどこまでのことを言っているのか、などの確認が必要になるのです。
これが「丁寧に聞いている人のわからなさ」です。
誠実であるがゆえの迷いなのです。
一方で、雑にしか聞いていない人なら、「“あのこと”とは、きっとさっきの話だろう」「あの時の話に違いない」などと勝手に決めつけて話し始めてしまいます。
それがたとえ見当違いであっても、クライアントの表情を見ていないので気づけません。
これが「雑な人のわからなさ」です。
同じ「わからない」でも、誠実さから生まれるものと、雑さから生まれるものはまったく別物なのです。
「なんでわからないんですか?」と責めてしまう危うさ
以上のように、カウンセラーが「どの部分のことを指しているのか教えてください」などと丁寧に確認するのは、雑だからではなく誠実だからです。
ところが、ここで自分の説明不足や配慮の欠如に気づけない人もいます。
その結果、無自覚のまま次のような反応をしてしまうのです。
クライアント:「なんでわからないんですか?(先生も周りの人と同じなんですか?)」
あるいは、
クライアント:「この前も言いましたよね。どうして覚えてないんですか?」
クライアント:「私のことを本当に見てくれてないんじゃないですか?」
これは、説明責任を放棄したまま相手を責める態度です。
本人にはそのつもりがなくても、相手には「あなたも結局、理解してくれない人なんだ」という決めつけとして響きます。
本来ここで必要なのは「自分の説明が抽象的すぎたかもしれない」「具体的に伝えていなかったかもしれない」という自己省察です。
しかし、その視点を持てないまま「なんでわからないんですか?」と反応してしまうと、せっかくの信頼関係を自ら壊してしまうことになるのです。
味方を敵にしてしまう恐ろしさ
ここで最も恐ろしいのは、そうした不満や落胆を「自分が勝手にしている」と気づけないことです。
本来は味方であったはずの相手を「やっぱり敵だった」と思い込み、人間関係を断ち切ってしまうのです。
しかし現実には、「味方だったのに、自分が敵にしてしまった」というケースの方が多いのです。
これは、無自覚の加害性がもたらす悲劇です。
特に厄介なのは、人生の大部分を「被害者」として生きてきた人にとって、自分が加害的になっている可能性を想像できない点です。
毒親に支配され、モラハラに苦しみ、「私は傷つけられる側だ」というアイデンティティが強く根付いているため、「自分が誰かを追い詰めている」とは夢にも思いません。
謙虚さの方向を履き違える
こうした人たちは、一見すると謙虚に見えることもあります。
「私のために時間をとっていただいてすみません」と恐縮する姿勢です。
しかし、その一方で「説明が足りなくてごめんなさい」「抽象的すぎて伝わらなかったかもしれません」という気づきや言葉は出てきません。
つまり、必要な謙虚さと不必要な謙虚さを取り違えているのです。
本来求められるのは「自分の伝え方を省みる」謙虚さです。
それを欠いたまま「存在そのものを申し訳なく思う」謙虚さを示しても、形だけの恐縮になり、相手に誠実さは伝わらなくなってしまいます。
こうして「わかってくれない」がエスカレートしていくと、やがて「それは絶対無理でしょ」というレベルの「察してほしい」を相手に押し付けてしまうようになります。
期待通りの反応が返ってこないと一気に0点評価を下してしまうのです。
相手は常に減点法で裁かれているように感じ、疲れ果ててしまいます。
当然ながら、誰も完璧には応えられません。
細かすぎる期待や基準に自分自身が気づかない限り、「またわかってくれなかった」と落胆し続け、関係は破綻に向かっていきます。
「自分に問題があるのでは」と思えない理由
本来なら、自分よりも多くの人と関わり、良好な人間関係を築いてきた相手に対しては「もしかすると自分の説明に問題があるのでは」と考えるのが自然です。
しかし、コミュニケーション経験が乏しい人はこの発想に至りません。
なぜなら、多種多様な人とやり取りする中で育まれる「自己修正の視点」が欠けているからです。
経験を積んできたならば、「相手に伝わらなかったのは自分の説明の仕方かもしれない」と思えることも、その回路が働かないのです。
だからすべてを「相手の責任」にしてしまいます。
機能不全家族の罪は本当に深刻です。
「わかってくれない」と嘆いているときは、ぜひ冷静に相手を観察してみてください。
もしその相手が他の人とは問題なくコミュニケーションを取れているなら、問題は自分の側にあるのかもしれません。
自分が悪いのか、相手が悪いのか
私はよく「自分が悪いのではないか」と思いすぎる人に対して、その思い過ぎをやめるように伝えています。
しかし一方で、「自分が悪いのではないか」とまったく考えない人にも問題があります。
人間関係において大切なのは、どちらか一方に偏らないことです。
結局、「自分の責任を考える視点」と「相手の責任を考える視点」の両方を持ち、行き来しながらバランスをとることが必要です。
右へ行ったり左へ行ったり、上へ行ったり下へ行ったりしながら(これは比喩です)、人は学び、調整しながら生きていくのです。
記事を書くときの懸念
最後に、このような記事を書くときに私が常に抱く不安を2つ書いておきます。
ひとつは、日々努力を続けているカサンドラ症候群の方々が「もしかして自分が“わかってくれない”と嘆く人なのでは?」と誤解して自分を責めてしまわないかということ。
もうひとつは、ASD傾向にある方が「この記事はまさしく自分の妻(夫)のことだ」と短絡的に決めつけてしまわないかということです。
こうしたテーマを語るときには必ずこの二つの懸念がつきまといます。
まとめと行動のヒント
「わかってくれない」と嘆くとき、そこには2つのパターンがあります。
カサンドラ症候群のように「十分に伝え続けても届かない」ケースと、「十分に伝えていないのに察してほしいと望んでしまう」ケースです。
後者に当てはまる場合、意識すべきなのは「説明の不足を相手のせいにしない」ことです。
少しでも「もしかしたら自分の言葉が足りなかったかもしれない」と振り返る視点を持てると、人間関係はずっと良好になります。
逆に、この視点を持てないと、せっかくの味方を敵にしてしまい、孤立感が強まっていきます。
だからこそ、「伝える努力」と「相手を観察する視点」をあきらめずに持ち続けることが大切です。